 |
||
|
|
||
 |
||
|
|
||
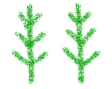 |
||
|
|
||
| ■品種 | スギゴケ科スギゴケ属 ウマスギゴケ・オオスギゴケ | |
|
|
||
| ■説明・自生地・環境等 |
園芸ではウマスギゴケとオオスギゴケがスギゴケとして扱われています。性質は同じで、双方に肉眼的な区別ができません。 コケ庭では石組みともよく合い、もっともよく使われる主要なコケです。 低地から山地のやや日陰地の湿った地上や腐植土のたまるようなところに群生します。また山の急斜面の岩盤の多いところなどにもみられる大型の種類です。 |
|
| ■成長形態 |
茎は5cmから20cmになり針のようにかたく、枝分かれはしません。葉は茎の中程から先によくつきます。湿ると葉を広げ、乾いてくると茎にくっつくようすぼまります。 生育し続ける種類で、春には芽先から再び伸び続けるため、主茎の長いものは20cmのものまであります。 日当たりの良い場所や圃場のものは黄緑色で葉も小型になります。生育環境により葉の大きさや色に大きな違いが現れます。 |
|
| ■植付け |
土を付け塊のまま採取します。 圃場生産されたものは土を付けた四角いマット状で、入手も容易です。畑土に少し川砂を混ぜた用土を使い、やや深めに土に挿し込みます。生産されたものはコテ等を使って表土とマットを完全に密着させます。コケの中に刷り込むように目土を施し、細いジョロで丁寧に灌水します。 蒔きゴケでは芽がある程度生えそろうまで乾燥させないように注意します。露地に直接蒔くよりも、育苗箱などである程度培養したものを露地に移植する方がよく定着します。 |
|
| ■管理 | コケ丈が毎年伸び続けるコケなので、あまり密生すると下からの新しい芽が伸びにくくなり、また見た目にもよくありません。 徒長抑制には底の平らな履き物で時々コケ踏みを行なうと効果的です。 あまりに伸びすぎたところは、コケを間引いたり、部分的な刈り込みを行います。 ・散水は朝か夕方に行い、日中、特に炎天下での水やりは控えるようにします。乾燥に強いと言われるコケの多くは、日中は葉を閉じて休んでいます。灌水により広がった葉を厳しい炎天下にさらすことは日焼けを起こすだけでなく、生育にも著しい影響を及ぼします。 ・冬の霜柱などでいであがって表土と剥離したコケは、暖かくなってから十分に表土と密着させます。 |
|
|
|
||
| サムネイルをクリックすると大きな画像を表示します。 | ||
 |
左が小佐越農園の山林に自生していたもの。 右は育苗ポットで半日陰地栽培したもの。 露地栽培のものは葉の開きが小さく硬くり、 林で自生しているものは葉を大きく広げて育ちます。 |
|
|
|
||
| 庭園材に使われるスギゴケの仲間で 左がスギゴケ(ウマスギゴケ)、 中がコスギゴケ、 右がタチゴケです。 |
||
|
|
||
|
|
||
| 通販のスギゴケ商品一覧 | ||
|
|
||
|
|
||